「また円安が進んでる…」「物価高でさらに生活が苦しくなるのか?」
2025年10月4日、自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出されたことを受けて、不安の声が上がる一方、市場はポジティブに反応しました。
円相場は一時1ドル=152円後半まで下落し、株式市場は逆に上昇──“円安・株高”の典型的な動きが出ています。(日本は輸出で稼ぐ大企業が多いので円安は株高に繋がりやすいです)
この状況を前に、実際に投資家としてどう向き合うべきなのか。
結論から言えば、高市新総裁の誕生は投資家にとってプラス材料です。
一方で、国の支出が増えることで円安リスクも同時に進むでしょう。
つまり今の投資スタンスとしては、円資産に偏らず、ドル建て・海外資産を中心に保有を続けるのが最も合理的です。
ただし長期的には円高に触れる可能性や、日本経済復興の可能性も秘めていると考えています。
まずは、高市新総裁の経済政策の中身と、それが株式・為替・インフレにどう影響するのかを整理していきます。
なぜ円安が進むのか──金融政策と財政政策のダブル要因
高市政権の経済方針は一言で言えば「金融緩和+積極財政」。
金融緩和とは、金利を上げて円を守るよりも、金利を低い状態にして企業や個人がお金を借りやすい状態を継続すること。
お金が市場に出回れば、相対的に通貨(円)の価値は下がる──その結果、自然に円安が進む構造です。そうする事で「お金回して経済を育てる」ことを優先しています。
かつての「アベノミクス」を踏襲していると言ってもいいです。
この姿勢が市場に「円は当面安いまま」というメッセージを与え、結果的に円売り・株買いが進んでいるのです。
① 減税・給付による円安圧力
高市政権は「家計を支える積極財政」を掲げ、生活支援を通じて消費を刺激しようとしています。
この方向性は短期的に経済を押し上げる効果がある一方で、同時に円安要因にもなります。
主な施策と規模
- ガソリン・軽油の暫定税率廃止(年1.5兆円規模の減税)
- 給付付き税額控除の導入(低・中所得層ほど恩恵が大きい)
給付付き税額控除とは、「所得に応じて減税+給付をセットで行う」仕組みです。
たとえば──
- 年収200〜400万円の層に10万円給付
- 年収600万円前後に5万円給付
- 年収800万円超は対象外
納税額が少ない層は、控除しきれない分が現金給付として支払われます。
つまり、家計支援と景気刺激を同時に狙う政策です。
ただし、このような減税・給付策は、短期的に可処分所得を増やすことで消費を押し上げる一方、国の財政支出を拡大させ、円の価値を下げる要因にもなります。
「家計支援」と「通貨価値の低下」という二面性を持つ──これが減税型の積極財政に潜む構造的な円安圧力です。
② 成長分野への投資による円安圧力
もう一つの柱が「未来を育てる積極財政」です。
これは、短期的な消費刺激ではなく、長期的な成長産業への投資によって経済の土台を強化するものです。
これから投資家が取るべき3つの軸
① ドル資産は“守り”でもあり“攻め”でもある
円安局面では、ドル建て資産の価値が上がります。
S&P500やオルカンを保有している人は、焦って動く必要はありません。
むしろ「為替に動じない姿勢」が、結果的に最強のリスクヘッジです。
ドル資産は今の日本経済に対しての“保険”でもあります。
② 日本株は“内需回帰”に注目
高市政権の方針は、防衛・インフラ・AI・宇宙といった内需型テーマが中心。
国土強靭化や再生エネルギー関連の需要は長期的に安定しやすく、
「海外依存ではなく、自国強化」に軸足を置いた銘柄が見直されつつあります。
③ 通貨の分散を“標準装備”に
長期的には、円という通貨への信頼が少しずつ問われ始めています。
米ドルやユーロ、金ETF、世界株など、通貨を分散させることでリスクを和らげる。
日本にいながら外貨で資産を持つ──それが今後のスタンダードになっていくでしょう。
投資家が取るべきスタンス──“分散”と“流れ”を意識する
結論、今の相場で大切なのは、焦って動くよりも「メガトレンドに沿った分散投資」を意識する方が安定します。
- ① 為替対応: 円安が進む局面では、S&P500・オルカンなどの海外資産を一定割合で維持。
- ② 資産分散: 日本円や株だけに偏らず、ゴールド・コモディティ・REITなど資産の性質が異なるものも組み合わせる。
- ③ メガトレンド重視: FANG+などのAI分野、エネルギー関連などのETF、宇宙産業など技術革新に沿ったテーマを長期で拾う。
つまり、為替や物価の波を読むよりも、
どんな世界の流れに資金が集まっているかを掴むこと。
これが、2025年の投資家にとって最も現実的で、ブレないスタンスです。
報道と市場のズレ──昨年の米大統領選を思い出す
ちなみに今回の総裁選、報道では“小泉優勢”という論調が支配的でした。
ところがフタを開けてみれば、高市氏が党員票で逆転。
キングメーカー麻生太郎氏の動きもあって、派閥の流れを見事に変えてみせました。
この「報道と市場のズレ」、どこかで見たことがある人も多いはずです。
そう──昨年の米大統領選です。
いわゆるオールドメディアは「カマラ・ハリス優勢」と伝え続けていましたが、市場は別の動きをしていました。
今回の日本もその構図に近いと思いますが、いよいよ民意と報道のキャズム(溝)が如実に現れてきた、そういった総裁選だったのではないでしょうか。(僕ら庶民にとっては良いことです)
そして希望もある──イタリアの保守政権が示した道
とはいえ、日本がこのまま沈むとは限りません。
イタリアでは2022年に保守派のジョルジャ・メローニ首相が就任して以降、税制改革や企業支援が進み、経済成長率と雇用が持ち直しています。
2025年5月にはムーディーズがイタリア国債の見通しを“ポジティブ”に引き上げ、ユーロ圏の中でも安定した経済運営を評価されました。
(出典:Reuters, 2025年5月23日)
高市氏が打ち出す「責任ある積極財政」「国土強靭化」は、この“イタリア型の現実主義”に近いものがあります。
一時的なバラマキではなく、国家を強くするための支出。
もしこの方向性が軌道に乗れば、日本経済は“円安を恐れず成長を取り戻す”段階に入るかもしれません。
インフラ投資や企業支援が国内生産力を高めれば、いずれは輸入コストの安定化や円買い圧力の回復につながり、一時的な円高への反転も起こり得ます。
つまり、短期的には円安による海外資産の恩恵を受けつつ、中長期では日本株が再評価される局面が来る可能性があるということです。
為替の動きを恐れるよりも、経済の回復プロセスそのものに乗る──それが今後の投資戦略の軸になるはずです。
まとめ──報道より市場を、短期より構造を
高市新総裁の誕生は、単なる人事ではなく「経済再構築の始まり」。
減税や給付で一時的に円安が進んでも、政策の狙いは“経済を動かすこと”です。
S&P500投資家にとっては為替の追い風を活かしつつ、日本の再浮上を見据えた資産設計をしていくタイミング。
報道に振り回されず、市場の“意志”を見る。
それが、2025年を生きる投資家のいちばん現実的なスタンスだと僕は思います。

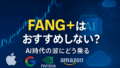
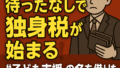
コメント