NISAブームとインデックス依存の現状
新NISAが始まって以降、日本の投資人口は急速に拡大しました。
2025年6月末時点でNISA開設者は約2,696万人。
そのうち500万人が「オルカン」または「S&P500」を保有しています。
つまり、日本人投資家の5人に1人がこの2つのファンドを選んでいる計算になります。
ちなみにオルカン(全世界株式)は「分散されているから安心」と言われますが、
実際の構成比を見てみると、アメリカ:約60%、先進国:約30%、新興国:約10%。
つまり、実質的には“米国集中型”のファンドです。
こうした状況は、日本全体が“強いアメリカ”の成長に乗っていると言えるので、
それ自体は悪いことではありません。ただ、
「なぜ今後もアメリカなのか」「その成長はこれからも続くのか」
この視点を持てることが、投資家としての次のステップにつながります。
「みんなが買っているから安心」では終わらない
SNSの普及によって、投資情報が一気に広まりました。
「オルカンが最強」「S&P500が安定」といった情報が拡散され、
多くの人が同じ方向に進むことで“みんなが買っている=安心”という構図が生まれています。
事実、オルカンもS&P500も教科書的な分析より、“自分の投資方針に自信が持てる結論”を見て、持ち続けている人が大半ではないでしょうか。
「自分の選択は間違ってない」「損をしないように背中を押してくれる情報」から“安心”を得たい、という心理です。
しかし、同調心理のまま始めた投資は、相場が下がった瞬間に不安に変わりやすい。
自分の中に「なぜこれを選んだのか」という構造的理解がなければ、
長期的に安心して持ち続ける事への不安を、常に背中に背負い続ける事になります。
過去データだけでは読めない「構造」を読む力
とはいえ、構造を読む力なんて、最初から誰も持っていません。
むしろ投資を始めたばかりの段階では、
“市場から退場しないようにする”ことの方がずっと大切です。
だからこそ、最初は投資で100点を取ろうとしないことが大事です。
完璧を目指すよりも、60〜80点で着地できれば十分。
少し肩の力を抜いた方が、結果的に長く続けられる。
これは数字を追うことではなく、“市場に残りづつけるための大事なマインドセット”です。
ただし現代の市場は、過去データだけでは読めない構造になってきているのも事実です。
金利差が縮まっても円高にならない
かつては、金利差が縮まれば円高方向に動くのが常識でした。
ところが近年は、金利差が縮小しても円安が続くという“逆の現象”が起きています。
その背景には、単純な金利要因ではなく、
- 米国株式市場への世界的資金集中(マグニフィセント7など)
- 日本の個人投資家によるドル建て積立(NISA経由)
- 地政学リスク下でのドルの安全資産化
といった構造的な資金の流れがあります。
もはや為替は“金利差の関数”ではなく、国際資本の流動構造を映す鏡になっているのです。
ゴールドが株高と同時に上昇している
もう一つの例が、ゴールド(金)と株の同時上昇です。
従来の常識では、ゴールドはリスク回避資産として“株と逆に動く”とされてきました。
しかし近年は、株高の局面でもゴールドが上がるという異例の状況が続いています。
背景には、
- 世界的な通貨価値の希薄化
- 実質金利構造の変化
- 各国中央銀行による金購入(外貨準備の多様化)
といった要因があります。
つまり、ゴールドは“恐怖の資産”から“信用分散の資産”へと位置づけが変化しているのです。
「相関の崩壊」は構造変化のサイン
投資の世界では、かつて“相関”がリスク分散の基本でした。
株が下がれば債券が上がる、円安ならドル高──そうした動きで全体のバランスを取ってきました。
しかし今、その相関関係そのものが崩れつつあります。
これは単なるノイズではなく、世界の資本構造の変化を意味します。
- 各国が同時に財政拡張を行い、通貨価値の均衡が崩れつつある
- “安全資産”ではなく、“実体のある資産”に資金が流れている
- テクノロジーやAIの進化が、産業連関を根本から変えている
こうした変化を理解していれば、「セオリー通りに動かない相場」にも動揺しにくくなります。
つまり、構造を読むことが長期的な安心につながるのです。
構造を読む投資家は「動的ポジション」を取る
構造を読む投資家が強いのは、
彼らが“固定ポジション”ではなく、“動的な視点”を持っているからです。
- 米国株一本ではなく、「なぜ米国が強いのか」「次に動くのはどこか」を観察する
- 為替ではなく、**資金の流れ(フロー)**を意識する
- チャートではなく、政治・技術革新・通貨の構造変化を見る
投資で大切なのは、“どこを買うか”よりも、
“なぜその資産が買われているのか”を理解しているかどうかです。
この理解こそが、どんな局面でも焦らないための“知的な防御力”になります。
まとめ──固定観念ではなく、構造理解で投資を続ける
インデックス投資は、本来とても優れた仕組みです。
“市場平均を取る”という考え方は、短期の勝ち負けに左右されず、
経済の成長を長期で享受するという合理的な戦略です。
しかし、合理性だけでは投資を続けることはできません。
ニュースや値動きに触れる中で、「このままでいいのだろうか?」という不安は誰にでも訪れます。
そんなときこそ必要なのが、構造を理解しておくことです。
チャートの裏側で何が起きているのか。
なぜ通貨が動き、なぜ金が買われ、なぜ株が上がるのか。
その背景を理解していれば、短期的な波に心を乱されることは少なくなります。
投資は、数字のゲームではなく思考の旅です。
未来を当てることではなく、世界を理解し続けること。
その積み重ねが、ブレない投資家をつくります。
「わからないことがあるほど、世界は面白い」──
そんな好奇心を持てる投資家こそ、世界の変化に最も強い存在なのです。

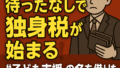
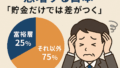
コメント